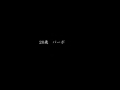雨あがる [DVD]
山本周五郎の原作に黒澤明の脚本という、誰が訊いても「最後の黒澤作品」
という印象を拭えない作品ですが、最近「博士の愛した数式」まで観て、
小泉堯史監督の作風を理解してみると、意外にも当時観たときには、処女作
として黒澤明へのレクイエムでありオマージュであると感じていた、全体に
漂う静かでゆったりとした時間の演出や、丹念に記録されたリアルな雨の
描写や繊細な山河の映像は、黒澤明へのそれではなく小泉堯史監督自身の
作風であることに気が付きます。
つまり、この作品は話題性としてのビックネームやキャッチフレーズで翻弄
されてしまいがちですが、処女作にして今なお貫かれている、自然の流れに
逆らわない、人間の機微をみごとに映像に定着させている精緻な作品である。
これをゆったりとした気持ちで眺めていると、ここに登場する様々な立場の
人々、不自由だらけで決して幸福ではないけれど、その思いは説明などなく
ても理解しあえる情緒で繋がっているという安心感。人情を押付けない謙虚
な自尊心の在り様など、古き良き日本人を見て、少々嬉しくなってきます。

心霊特捜 (双葉文庫)
岩切大悟は神奈川県警刑事総務課に所属しているが,県警のR特捜班との連絡係として勤務している。"R”は実は「霊」の頭文字でR特捜班は別名,心霊関係が絡む事件の特捜班『心霊特捜班』と呼ばれている・・・
6編からなる短編集。霊に絡んだ事件をR特捜班に所属する霊能力(!?)を持った3人と,持たない班長,そしてどちらかというと霊に弱い主人公の大悟が関係していく短編である。それぞれは,登場人物が同じと言うだけで関連性はなく,非常に読みやすい物語である。しかし,それだけに後に何が残るというわけではない・・・気軽に読むには最適な本である。

小説日本婦道記 (新潮文庫)
題名がすごい、封建的である。よく読んでみなければ、「何じゃこれワー」とのたうつ現代の婦女子も多かろう。巻末の解説によれば、「女ばっかり不幸になる/犠牲になる」との批判が多かった作品であるという。しかしながら、しっかりわきまえた現代人なら、この小説を「日本女性かくあるべし」などと、読めるはずもない。実は周五郎の一つの隠れテーマである「人間他人をどこまで赦せるか、信頼できるか」を表現するのにたまたま、女性が主人公であったほうが収まりがいい、伝わりやすい、それくらいなもので、題名から連想される教導的なものではけっしてない。むしろ、周五郎の持つ現代性というか、女性への尊敬の念を強く感じさせる作品と思うがどうであろう。くれぐれも女性の理想像として読まないでほしい。それはつまらない読み方ではないか。

その木戸を通って [DVD]
市川監督と気心の知れた達者な俳優さんたちが多数出演していて見ごたえがあり、ロケーションやセットの素晴らしさも特筆すべきものがあるのですーが、どうも中途半端な印象が拭えません。 まず、あの室内シーンの見事な照明、やはりあれはフィルムで撮ってこそ映える技術ではないでしょうか? 闇の部分がまったくない、軽い映像になってしまっています。 時代の趨勢にあえて逆らうようなことを書きますが、ハイビジョンとかデジタル映像というものは、動物ドキュメンタリーやスポーツ中継、SFX作品にはいいのでしょうが、人生の重みとか、人間の心の機微を捉えるにはむしろ不向きのメディアではないかと私には思えます。 加工・保存がし易いー、という利点は同時に軽めの映像になるーというマイナス点も抱えていると思うのです。 結局、従来の映画でもTVドラマでもない、不思議な雰囲気を持った映像作品になっており、そこがいいのだ、という見方もあるのでしょうが、これはやはり狙って出しえた効果ではなく、偶然の産物に過ぎないのではないでしょうか。
技術的な面はさておき、内容の点でも、なんだか変な作品です。 最後まで意味が分からずじまいの“その木戸”のコンセプトや、あいまいなクライマックス。 愛する人とあのようなかたちで別れねばならなかった主人公が、“俺の人生はほどほど幸せだったと思う”というのは、17年間の彼の軌跡が描かれていないだけにかなり強引な結末に見えます。 ストーリーを頭から追っていったら、この人は無理やり自分は幸せだったと思い込もうとしているような構造になっており、これじゃまるで悲劇です。 技術面、内容的にも、市川監督第一級の作品とは言えない出来になっていると私は思います。

抱擁、あるいはライスには塩を
世代をこえた長編小説は時系列的に書かれるのが通常であるが、物語は、1960年代にいったり2000年にいったりする。登場人物も当然祖父母から正妻、愛人の子供達と登場人物も多く、また、ロシア生まれの祖母から、70年代に生まれた子供達ととても幅広いのだけど、一つ一つの章において丁寧に一人の人物の最も重要な思いを綴っているのが印象的でした。
期せずして、この時系列を超えた表現と登場人物の限られた次期における濃縮された経験と感情にフォーカスをするこの書き方かた、私は不思議と家族の本質と人間の記憶はそんな風に存在するのではないかと思うようになりました。そういう意味では大変影響を受けました。
やはり江國香織のような文芸作家はこのような小説こそを書くべきではないかと思うのです。なぜなら文学とは根本的に人生と人間の心を探求するものであるのであって、そして、一人一人の人生はそのきらきらとする場面や悲しみで言葉を失うような場面の不連続な積み重ねに他ならないのではないか、この小説を読んでそういう思いをはっきりと持つようになったと思います。
一部屋一部屋の装飾の描写、登場人物の服の生地の色と感触の具合、庭の植物や小さな生き物がこの小説では映画を見るよりもはっきりと浮かんでくるのはさすがに江國作品だと思います。
それではこの小説の伝えようとしたメッセージとは何かと問われると難しいのですが、’家’とは物理的というよりも関係の産物であり、複数の感情のインターアクションの産物である事、そして、これまでの江國作品から何よりも踏み込んだのは、彼女の人生観を描いた事だと思います。偶然と必然と運命によって人生は築かれていくのであるけれど、ひとは、家=人との関わり によって人生を紡いでいってきっと全ての人に多かれ少なかれ必ず宝物のような記憶が人生によってもたらされることが人生の終焉や悲しみがあっても生きる価値がなおあるのではないかと軽やかな江國口調で語られていると思います。