
沈黙 (新潮文庫)
島原の乱が鎮圧されて間も無い「キリスト教禁制」下の日本において、棄教を迫られるのポルトガル司祭・ロドリコを描いた、余りにも有名な小説です。
考えさせられる事が数多ある作品でした。
宗教とは何か、信仰とは何かという事のみならず、生死に拘わる困難な状況に直面した際に人は何を考え思うのかといった、人の在り方という根源的なものも描いている様に思えてなりません。
事の正邪を論じた単純な作品ではありませんが、敢えて述べるならばロドリコ、フェレイラ、キチジロー、誰もが正しいと言えるのではないでしょうか。
作品中、キチジローこう叫びます。
「(前文略)踏絵ば踏んだ者には、踏んだ者の言い分があっと。踏み絵をば俺が悦んで踏んだとでも思っとっとか。(中略)俺を弱か者に生れさせおきながら、強か者の真似ばせろとデウスさまは仰せ出される。それは無理無法と言うもんじゃい」
人が生きていくうえで生じる迷いや恐れといった、負の感情を除いて幸福へ導き生きる力(希望)を与えるもの、いわば人の弱さを補うものそれが宗教、そして信仰だと私は考えていました。
では、キチジローのこの苦しみは何なのか?
読了後、私は天を仰いでこの事について考えましたが、考えはまとまりませんでした。おそらく愚陋な私には生涯、答えを出す事が出来ないでしょう。
余談ながら遠藤周作といったいわゆる「純文学」的な作品は、難解な語句の使用と高遠な表現などで、さぞ読み難いものなのだろうという先入観がありました。
しかし、実際にはその様な事は殆どありません。
平易な文体に因り人口に膾炙するからこそ「名作」と称されるのだと気付き、自分の不勉強さを思い知らされました。

十頁だけ読んでごらんなさい。十頁たって飽いたらこの本を捨てて下さって宜しい。 (新潮文庫)
相手(読み手)の気持ちになって書くということは、言い当てているようで実は難しい。
誰しも自分の気持ちを伝えるために手紙を書くのだが、思いが強いほど一方的な通達になったり、相手の気持ちを勘違いする。
本書は、ラブレターや冠婚葬祭の文例を挙げながら、どこがいいか、いけないかを端的に示してくれる指南書だ。
無難すぎる文、エゴの強い文、何を言いたいのか分からない文などの問題点が分かるようになっている。
よいとされる文例も載っていて、さりげない気遣いの言い回しはなるほどと思える。まとめると、形式にとらわれず、突然受け取った身になって、分かりやすさを重視して書く。
私のような凡人に、気の利いたフレーズがポンポン思い付くわけではないのだが、程よい加減を何となく自覚できる。
男性目線であることと、昭和の香りが強いので、今読むと古臭いと思う人が多いかもしれない。
でも、発想を変えて読めば、ビジネスの現場で忘れがちな基本を教えられているようにも感じられた。いい本。
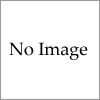
深い河 [VHS]
熊井啓と三船が組んだ最後の一作。三船は頭の病が進行し、半ば朦朧としていたという。撮影もしばしば中断したらしい。しかしである、画面に姿を見せる三船からはそんな雰囲気は微塵も感じられない。さすがである。出番はそんなに多くないが、花火をバックに登場するシーンなどは夢のような美しさである。痩せた三船に往年の迫力はない。それでも、沼田耀一に日本酒の盃を投げつけるシーンは、ハッとする凄みがあった。インドロケも美しかったが、自分が印象に残る名場面は、やはり三船の勇姿である。早くDVD出してほしい。

愛する [VHS]
わたしはレンタルビデオ店でビデオのパッケージを見るまで、映画「愛する」の存在を知らなかった。「全国でロングランヒット」と書かれてあったが、私は知らなかった。 あるキリスト教の教会の掲示板に、渡瀬恒彦主演の「親分はイエス様」という、凄い題名の映画のポスターが張ってあったのを見たことがある。「愛する」も「親分はイエス様」もキリスト教の信者向けに作られた映画であるのだろう。 そんな「愛する」をクリスチャンではない私が観て抱いた感想は、不覚にも涙を流してしまったくらいに、感動した。信仰を持たない私が感銘を受けた理由は何なのであるか、正直に申し上げれば、私にも判らない。 ハンセン氏病が主題である映画といえば、みなさんご存知の「砂の器」がある。「砂の器」は新劇の故加藤嘉、新国劇の緒方拳がクライマックスの場面で、泣き叫び、観客を涙に誘う仕組みになっていた。 「愛する」にも、主演の渡部篤郎、酒井美紀が号泣する場面はある。ただ単に私も涙に誘われて、涙しただけなのか。私はキリスト教の「愛」が今一つ良く判らないでいる日本人の一人である。 信者ではない。出演者の演技に感銘を受けたのでもない。熊井啓の映画のファンでもない。ストーリ自体にも、率直に申し上げれば、空々しさを感じてしまった程である。 多分死ぬまで判らないような予感がする。それでも良いと、私は考えている。

深い河 (講談社文庫)
インド、特にガンジス河のほとりのバラナシを舞台にした純文学。
妻を亡くしてから初めて愛や妻との縁について考え始めた磯部、本当の自分を誰にも出せず九官鳥等の鳥にだけ本心を話すことのできた沼田、太平洋戦争時にビルマで地獄のような体験をした木口、結局自分は誰のことも愛することなどできないのだと考える美津子、そして美津子の大学の同窓生でキリシタンながらヨーロッパ的な善と悪を峻別する考え方に共感できずにいる大津、それぞれの人生を微妙に絡めつつ、裕福な者から貧しい者まで全ての者を分け隔てなく受けとめる母なる河・ガンジス河が彼らをいざなう。
人生とは愛とは、そして神とは…不思議とそんなことを考えたり語りたくなってしまうバラナシ、そしてガンジス河。
「他の国・民族が持つ信仰とはもちろんのこと、たとえ自分の周りの人々が持つ信仰とは違えども、その人がその人の育った環境や価値観から培った信仰であれば、それは人それぞれであって良い」とこの本に教えてもらった気がする。
インド(特にバラナシ)へ行ったことのある方は共感しながら読めるであろうし、行ったことのない方が読んだらインドへ1度行ってみたいと思うような本であると思う。
ソレデハ…







