
LIVE AT OPEN THEATRE EAST 1993 & CONCERT 96 [DVD]
1993年7月25日、よみうりランド・オープンシアター・イーストでのライヴを収録。DVDを観ると分かるが当日は雨で、ピアノ・ベース・ドラムの上には雨よけの透明のテントが張られ、観客はほとんど全員がカッパを着ての野外ライヴという極めて珍しい状況での収録になっている。
そんな珍しい状況でのライヴを3人、特にキース・ジャレットは楽しんでいる。ビックリするくらい何度もアンコールに応えたり、曲の合間に呑む水の入れ物に雨を入れてみせる仕草をしたりと、実に楽しそう。当然演奏の方も絶好調で最後に行くほど素晴らしい。
彼等の演奏する様はまるで音楽を食べているかのようだ。苦いなー、という顔をしながらドラムをさばくディジョネットや、キースのピアノになるほど次はこうくるか、という美味しそうな顔をするピーコック。トップサイダーとおぼしきスニーカーで小刻みにペダルを踏み、蠢くキース。どれもなかなかいい。DVD故に音もCDよりずっと良く、ライヴはもうこれから全部DVDで出して欲しいな、と思わせる演奏だ。
めったに観られない雨の中のスタンダーズ。必見です。

Rio
2011年4月11日、リオデジャネイロ、Theatro Municipalにてライヴ録音。2009年『テスタメント』以来、約2年振りとなるアルバムである。ぼくもキース・ジャレットのソロ・ピアノの全てを聴き続けている一人だが、この作品を聴いて気がついたことを書き留めておきたい。
まず、彼のソロの一曲一曲が短くなっているということに気がつく。昔は、『Lausanne, March 20, 1973』を1時間4分54秒で一曲といった感じだったわけだが、この『Rio』は15曲の小曲の作品集のようになっている。これは言ってみればショパンの12曲からなる練習曲集のような構成になっていることを意図しているのだと思える。そしてそれを構成する各々の曲に広い分野の音楽的要素を組み込んでいるのを感じる。新ウィーン学派→ジャズ→ブルース→ロマン派といった感じでより広く深く音楽という世界の極北から極南を表現しようとしている気がすごくするのだ。
それはクラシックの世界で言えばドビュッシー、ラヴェル、サティといった時代の作曲家が旧来の音楽にとらわれず、インドネシアのガムラン音楽に影響を受けたり、7th→9th→11th→13thといった、ジャズで後付けされた言葉で言えばテンション・コードを積極的に音楽に導入し、曲作りをしてきた世界をもっと広げて、ブルースとか新ウィーン学派の12音階とかあらゆる語法で作品を構成し、ひとつの作品集とする。しかもそれを即興かつライヴで実践するという試みだと思えるのだ。それは今までのキースがソロ・ピアノをもう一段上のソロ・ピアノへと向けるべく進み出しているのだと思う。
遥か未来のリスナーはこのアルバムを語る時、ドビュッシー、ラヴェル、サティの試みと比較しつつ、それをより推し進めた姿として語るような予感がする。そんな傑作である。
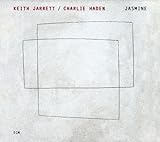
Jasmine
この音楽にワインは駄目だ。
絶対にウイスキーじゃないと駄目だ。
少しピート香の効いたスモーキーなヤツ。
10年は樽で熟成されてタンニンが染み出して少し渋みを含んだ綺麗な琥珀色の芸術。
なんて調子良く筆をすすめてみても、
実はその手に握られてるのは大五郎だったりする。
この音楽は大五郎をマッカラン18年に錯覚させてしまうくらいの芳醇な香りの琥珀色の音と言える。
音数はすごく控えめで
その”間”に人生の渋みが溶け込んだよう。
自分はこれを妻と聴けない。
一言も交わさず、息をひそめて聴き込んでしまう。
キースのデュオって他に記憶がない。
一方ヘイデンはといえばデュオのマエストロだと認識してる。
ピアノだけでもケニー=バロン、ゴンサロ=ルバルカバ、ハンク=ジョーンズ, デニー=ザイトリン。
他にもメセニーとのデュオもある。ギターのエグベルト・ジスモンチとのライブ盤もある。
それらはどれも例外なくすばらしく暖かさに満ちたもので愛聴盤となっている。
ヘイデンがピーコックでも作品の内容にたいした変わりは無かっただろうと言う評者もいますが、
ピーコックではこうはいかなかったと思います。
彼とでは丁々発止のプレイを期待してしまう。
それはそれですばらしいモノになったとも思います。
しかしヘイデンは過去のデュオ作から内圧の圧力を圧として引き出すよりも
もっとナチュラルで柔らかい部分を引き出してくると思うんです。
自分はバリバリのインタープレイをここには一切期待などしていなかった。
しかし予想以上にここではとろけるぐらいの仕上がりを聴かせてくれた。
キースとヘイデンのここでの対話は張りつめるような緊張感は支配してない。
この音楽を作り上げる喜びに満ちてる。
ヘイデンがキースにお帰りと言っているようだと言えば感傷的に過ぎるか。
でもキースのピアノには喜びが舞っている。
そこがヘイデンの凄さだと思いますしキースのランドマークの一つになると思うんです。
確かにエポックメイキングな問題作でない。
でも音の間に人生が溶け込んだような音楽もまたジャズとして一つのあるべき姿だ。
音楽家がふと音楽に立ち返った時にこの音楽が鳴っているとすれば、
それはジャズの奥深さを鳴らしているのと同義語だと思うんです。
まずは一人で耳を傾け最愛の人に勧めたくなるアルバムであるのは間違いないと思います。

ザ・ケルン・コンサート
既に何度もCDが発売され、多くの方が絶賛されているので、私ごときにもはや付け足す言葉はありません。1975年1月24日にケルンで奇跡がおこりました。その瞬間を見事に捕らえた録音が素晴しい。まるでピアノの音の一粒一粒を手でつかめるかのようです。アナログ時代の録音の極致と言っていいでしょう。キースのハミングや足踏みの音もしっかり録音されていますが、全く苦になりません。それらを含めてこの巨大な作品が成り立っているのです。大学生のとき、ほとんど毎日LPを聴いていたのを懐かしく思い出します。今はさすがに毎日というわけにはいきませんが、時々CDを聴き返して、現実に立ち向かう勇気をもらい続けています。

The Melody At Night, With You
久しぶりに引っ張り出して再生ボタンを押したのですが、
まるで昨日作られたかのような音が部屋いっぱいに広がり
すべての曲に魂が溢れ、すべての曲が人生をすべて詰め込んだ
ラストピアノのように響いてくるのです。
本当に素晴らしく、『CDを』というより『音そのものを』
大切にしたいと思わせてくれる名盤だと心から思います。
私が聴くといつも思い浮かぶのは、秋というには少し早い
夏の終わりの切なさです。とても懐かしい気持ちになります。






