
マリリンとアインシュタイン [DVD]
テレサ・ラッセル=マリリン・モンロー(らしき女優)
マイケル・エミル=アルバート・アインシュタイン(らしき科学者)
ゲイリー・ビジー=ジョー・ディマジオ(らしき野球選手)
トニー・カーチス=ジョセフ・R・マッカーシー(らしき上院議員)
この物語は、全てフィクションである。
このカルトにしてポップな怪作が、ついにリリースである。
1954年、NY。とあるホテルに、この時代のアメリカを象徴する4人の人物が集う。
地下鉄の風で、スカートがまくれ上がるシーンを撮り終えたばかりの女優。彼女と離婚の危機に瀕し、浮気疑惑に取り憑かれているスター野球選手。自由主義思想の追放を目論む上院議員。その公聴会への出席を要請されている、天才物理学者。
これは、「もしあの人たちが出会ったら」という設定の下で展開する、仮想の会話劇なのだ。
まずこの映画が面白いのは、この人物たちの名前を一切出していないのに、明らかにマリリン、アインシュタイン、ディマジオ、マッカーシーだと一目瞭然だという事。実はこれこそ映像メディアたる映画の凄いところで、これを言葉で表現しようとすれば、前述のように「・・・らしき」など、持って回った言い方をするしかないし、それは断言しているも同じである。
マリリンを演じるテレサ・ラッセルは、よく見れば大してマリリンに似ていないのだが、あの髪型とドレス、そしてマリリン風のメイクをしただけで、マリリンにしか見えなくなってしまうから不思議だ(演技もかなり素敵です)。こうして、作り手の確信犯的なポーカーフェイスで、観客が持っている先入観を巧く利用し解釈させて、いつの間にか共犯関係を作り上げてしまうメタな面白さがこの映画にはあるのである。
憎らしいくらいにトリッキーな(そして、トリッキーであることを全く意識させない)本作の監督は、『地球に落ちてきた男』や『美しき冒険旅行』などで知られる映像の錬金術師、ニコラス・ローグ。本作では、いつもの実験精神横溢する映像テクニックの連打はなりを潜め、むしろMTV的なポップでオシャレな映像づくり。ただし得意のフラッシュバックは健在だ(笑)。
原作はもともと舞台で、原作者テリー・ジョンソン自らが脚色。いかにも舞台劇風に、キャラクターたちが出入りする事で「if」な会話が生み出される。
マッカーシー×アインシュタイン
アインシュタイン×マリリン
ディマジオ×アインシュタイン
マリリン×マッカーシー、などなど。
中でもやっぱり面白いのは、邦題にもなっているマリリンとアインシュタイン(この二人が事実上の主人公と思われる)のシーン。もともとモンローは「寝たい男ナンバーワンはアインシュタイン」という発言をして世間を驚かせたというが、まさに夢のランデブーが映画で実現。アインシュタインへのリスペクトを証明するために、雑貨屋で購入した車や兵隊のおもちゃ、懐中電灯、風船などを使って部屋中をドタバタ駆け回り、マリリン式に「特殊相対性理論」を嬉々として解説する様子、それを楽しそうにウンウンうなづいているアインシュタイン、お二人とも例えようもなくキュートだ!余談ながら、超文系の筆者にもすごく判りやすかった。マリリンの説明(笑)。
本作の俳優たちは、みな見事に「キャラクター」としてのそれぞれの人物を演じていて、巧い。先ほども書いたが、似てないのに妙に説得力があってプリティーなテレサ・ラッセル。ひたすら無骨で粗野(ガタイもいい!)な感じのディマジオを演じたゲイリー・ビジー。マッカーシーのクソ野郎ぶりを、アイロニーたっぷりに演じたトニー・カーチスも抜群。そして特筆すべきは、アインシュタイン役のマイケル・エミル。映画出演4作目とは思えない存在感。科学の探求を国家に利用され、有名であることに疲れた自嘲的なキャラクターを名演。
マリリンとアインシュタインは、自らの名声や業績によって自己を喪失しかけ、苦悩しているキャラクターだ。マリリンはセックス・シンボルとしての自分と、世間が知らない本当の自分の間で引き裂かれた哀れな女性である。(バーに貼られている、デビッド・ホックニーによるフォト・キュービズム=バラバラに寸断されたマリリンのコラージュが彼女の心を象徴している)アインシュタインは、広島に落とされた原爆に心を痛め、戦時下の原子力開発進言書簡に署名した事に責任を感じている。彼の懐中時計は原爆が投下された(8月6日の)8時15分で止まったままだ。一方ディマジオは、己の名声にしがみつく事で、アイデンティティーを必死に保っている人物にも見える。自分が今まで13回もベースボールカードになったことをしきりに自慢するのがその好例だ。そしてマッカーシーは、色々偉そうにまくしたてても、結局は国家の大義名分のために働く歯車にすぎない。
ニコラス・ローグは人間ドラマに興味はない。ロマンチシズムやリリシズムを拒否し、ひたすらアートとしての映画の可能性と、人間心理の奥深く潜むオブセッションを探求した監督だ。だからこの映画は人間ドラマとは言えない。個々のキャラクターの苦悩に共感し、それを描こうとする映画ではないのである。「戦勝」「原子力」を背景に、繁栄に溺れていた'50sアメリカがいかに巨大でがらんどうな張子の虎だったかを、その時代のイコンとも言えるキャラクターたちを「成功者」ではなく「喪失者」あるいは「空虚な人間」だということを描く事で浮き彫りにしていく、一種の風刺劇。そのための会話劇なのだ。
原題の「Insignificance」=【無意味な、とるに足りない、つまらない事】といった意味からも、それは明らかだ。
本作が撮られた'85年は、MTV文化全盛の時代。日本では経済バブルと呼ばれたこの時代は、アメリカでも「Big Nothing」と呼ばれている。'90年代から21世紀にかけて失速していく経済大国の、最頂点の時代。未来は繁栄していると信じきっていたこの時代の能天気ぶりは、ある意味で'50年代「Big Nowhere」と呼応する。だから、この映画の中のビジュアルは、「リアル」ではなく、あくまでも「ポップ」なのである。ラスト、アインシュタインが、マリリンの去り際に幻視するヒロシマの原爆投下。ホテルの一室は瞬時にあの日と同化し、窓ガラスや壁が爆風で吹き飛び、マリリンは死の炎に包まれる。しかし、その直後に描かれる広島とおぼしき破壊された市街のセットは、いかにもミュージックビデオのセットのような風景である。神社の鳥居も申し訳のようにポツンと立っていて、そんな中途半端なことをするならいっそ見せないでほしいと言いたくなる、日本人としては非常に複雑な気分になる映像だ。
しかし、いま観直してあまりにも皮肉に感じるのは、この映画の中で描かれている事は、今の日本に通じるものがあまりにも多すぎるのでは?という事だ。
映画の冒険者、ニコラス・ローグが'80年代に放ったちょっとした遊び心は、20年以上過ぎた今、なぜか重くのしかかってくるのである。
さて、本作にはMTV時代を象徴する要素として、もうひとつ音楽がある。何とサントラ・プロデュースは、プロパガンダやアート・オブ・ノイズを手がけたZTTレーベル!OPタイトル・バックを飾るのは、ウィル・ジェニングスが気だるく歌う「When Your Heart Runs Out of Time」。そしてスタンリー・マイヤーズ作曲・演奏による、フルバンド・ジャズ・スタイルのゴキゲンな主題曲「A Dog of a Night」。幻想シーンを盛り上げるハンス・ツィマー。ロイ・オービソンの「Wild Hearts」、テレサ・ラッセルがモンロー風に歌う「Life Goes On」(どこで使用されているか確認できなかった・涙)さらにギル・エヴァンスがジャズ風にアレンジしたモーツァルトの「交響曲第41番・ジュピター」(これがキッチュで面白い!)といった、まさにノンジャンル・コラボ。'50年代の時代感の中でも、音楽センスは'80sアートしているのだ。
最後に、待望のDVD化に拍手。『マリリンとアインシュタイン』という邦題には、内容を知らなくても惹かれてしまう不思議な魅力と響きがある。心に深く突き刺さるような作品ではないが、何年かに一度、観直したくなる映画なのだ。
あの、アート感あふれるポスターの傑作イラスト(炎の玉と化したマリリンの頭部に、数式が踊っているのが秀逸)を採用したパッケージも素晴らしい!

ライヴ・アット・フィルモア・ウェスト
このCD、私が持っている全ての音源の中でも、最もソウルフルなものかもしれない。
1曲目「メンフィス・ソウル・シチュー」がメンバー紹介を兼ねているのだが・・・
まずドラムスのBernard Purdie。そしてギターにCornell Dupree。
キーボード、Billy Preston。エレピがTruman Thomas。エレベがJerry Jemmott。
コンガにPancho Morales。
そして、The Memphis Horns! このホーン隊抜きではありえない!
そして勿論saxesがKing Curtis。
2曲目”A Whiter Shade of Pale"ではカーティスがソプラノ・サックスで、ヒット曲を痺れるバラードで。
3曲目はレッド・ツェッペリンの”Whole Lotta Love"
最終曲”Soul Serenade"(これもソウル・バラード)まで揺れっ放しの痺れる演奏。
続きはAretha live at Fillmore Westを聴きましょう。
キング・カーティスはこの後すぐに不幸なトラブルに襲われて亡くなった。
This amazing album is one of the greatest he left us.
(ソウル・ファンは勿論聴いているでしょうが、ジャズ・ファンも一度は聴きましょう!)
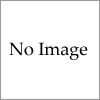
バッド・インフルエンス~悪影響~ [VHS]
バッド・インフルエンス −悪影響− BAD INFLUENCE (1990)
監督:カーティス・ハンソン
製作総指揮:リチャード・ベッカー/モリー・アイゼンマン
製作:スティーヴ・ティッシュ
編集:ボニー・コーラー
撮影:ロバート・エルスウィット
美術:ロン・フォアマン
マイケル/ジェームズ・スペイダー
アレックス/ロブ・ロウ
最近 昔観た 面白かったのに DVD 化されていない映画をヴィデオで集めてまして この作品も面白かったと記憶してたので購入。 レンタル・アップでもいいや、 と安く買ったのだが やはり劣化している感は否めない。 私が購入した物は画像的には それほど影響はなかったが 音声の部分で少し残念でしたね。 ステレオがモノラルになったり ならなかったり。 会話では そんなに気にならなかったが 音楽が導入されるシーンでは少し気になった。 久しぶりに観ましたが内容の方は やはり面白かったです。 今回 観てビックリしたのは ジェームズ・スペイダー演じるマイケルの婚約者役で 「デスパレートな妻たち」 シリーズのブリー役の女優さん マーシャ・クロスが出演していた事。 当然ながら若い! んで 今思えば監督は私の好きな 「ゆりかごを揺らす手」 の方なんですね。 主演の 2人はタイプは違うけれどハンサムな俳優さん。 真面目な優等生サラリーマンを演じるのは 「セックスと嘘とビデオテープ」 のジェームス。 ジェームス演じるマイケルがバーで絡まれているのを助け そこからマイケルの人生に悪影響を与える極悪人を 当時 自らの性交を録画したヴィデオが流出し 大きな話題となったロブ・ロウが熱演。 このスキャンダルもあって この作品にも注目が集まった。 ロブ自身はトホホ (死語か?) な話だろうが 製作者側にしてみればラッキーなトラブルだったのではないでしょうか (笑) ロブではないが それらしいシーンも出てくるし。 とにかく そのロブが演じるアレックスが強烈に悪い。 最初はマイケルの親友にもなれそうな良いヤツっぽかったのに あまりにもヤリ過ぎの行動にマイケルが彼を突き放した途端 悪魔に変貌する。 マイケルもダメ×2 なんですが アレックスは最悪。 でも味方に付けたら頼もしいとも思う (笑) ここまで徹底して敵を追い込むのはスゴイですよ。 アレックスがマフィアのボスなら かなりイケイケの組織になるだろう。 でも 彼を見ているうちに可哀想に思えてきました。 何も誰も信じられずに悪事を重ね 彷徨うアレックス。 彼に必要なのは ”親友” だったのではないだろうか。 この酷い仕打ちは それを期待させたマイケルに 裏切られたと思っての行動だったのではないか。 彼は確かにマイケルが望んだ事を叶えてやった。 間違ったヤリ方だが 彼なりの誠意だったのではないだろうか・・・ ラストが あんな感じだったのは忘れてましたが 今回の鑑賞で 何か もう1つ捻りが欲しなぁ〜と思いました。 そこ以外は面白かったです!

ライヴ・アット・フィルモア・ウェスト
まさにソウルパワー!!しかも勢いだけではなく、かなりの技量をもった圧倒的名な演奏です。マスタリングも当時の録音から察するにかなり丁寧、ボートラもいいです!相変わらず拘ったRHINOのスタンスを垣間見れます。
ところで、B.PERDIE大先生の若き日の元気な超グルーヴドラムがそのサウンドと相俟って強烈、ベースも含めたリズム隊のウネリは相当なノリとなって迫ります!PERDIEフリークは必携!
それに加え、押し引きをわきまえた、実は繊細なテクニックにも惚れ惚れするKING先生、これを聴くまで認識はなかったのですが、ワウまで噛ませたかなりエレクトロニックな大胆なフレージングも炸裂、しっかりした演奏でありながらノリノリのまさにグルーヴで一気にファンク、R&Bを聴かせてくれます。
当時の常套句とはいえ、単にノリノリだけではなく、スローな曲で聴かせどころも準備するなど、サービス精神も極めて旺盛!
徹頭徹尾ひたすら揺れっぱなし、ということでは物足りない方もいらっしゃるかもしれませんが、それが渋いんです!
こんな曲聴かせてくれる人、今となってはそうはいませんね。
PURDIEフリークは当然のこと、あの頃の熱いミュージックマンたちの思いは痛感すること請け合い、ブラックミュージックを辿るうえでは看過できませんよ!







