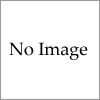
PROPAGANDA [VHS]
今、YMOのビデオを買うというのは、熱狂的なファン以外なら、その理由の方に興味が湧くでしょう。このビデオは、横浜の根岸・森林公園内にある、旧競馬場跡がステージとなっているという点が、買いです。この競馬場跡は、現在では米軍から返還されたものの、フェンスで高く覆われて、立ち入り禁止となっており、こうして昔の映像で偲ぶしか無い訳です。日本で最初の競馬場跡(といっても当時は上流階級の社交場的な存在ではなかったかと思います)は、長年の風化によって、何とも味が出ており、このビデオを観て興味を持たれた方は、当地に行かれて、往時に思いを馳せるのも一興かと。こういう枝葉末節で映像を鑑賞するのも、許されるかと思います。

path_ ryuichi sakamoto playing the piano 2009 - 2011 [DVD]
まだCDしか聞いてないけど、このCDはいいですよ。
ピアノの音がすごくリアルです。聞いてて気持ちのいい音です。
韓国の人って、ピアノの最後の音が完全に消える前に
拍手するんですね。日本人だと完全に音が消えてから
拍手すると思うけど。どっちがいいとかはないけど
国民性?なんでしょうか。
演奏中の咳払いなども割と少なく、さほど気にならなかったです。

THREE
クラシック好きなら当たり前のことだけど…
同じ曲でも演奏家を変え、
あるいは同じ演奏家の別の演奏を聴き比べ、
ああでもないこうでもないと鑑賞に浸りたい。
「THREE」はまさにこのような鑑賞に耐えるアルバムだ。
まず、ジュディ・カンという新しいヴァイオリニストが素晴らしい。
表現力が抜群に高くジャキスとの息もぴったり。
教授のピアノがメインで弦が添え物のように扱われていた1996に比べ、
ずいぶんピアノ・トリオらしくなった。安心して鑑賞できる。
耳を傾けると、3人の上品なおしゃべりに時間が経つのも忘れる。
「THREE」というタイトルの由来はこの辺にあるのかも知れない。
「1996」と比べて大きな変化は、さらに二つある。
全体的にテンポをかなり遅めたこと、
そして、コントラストを弱めたことだ。
そのせいで、人によっては緩慢な印象を受けるだろう。
教授はもっとテンポを遅くしたかったという。
私はこの発言に教授の思想を読み取る。
昨今の音数と音圧を極限まで詰め込む、
音楽シーンへのアンチテーゼなのだと思う。
その思想は現代の社会へと向けられているようにも感じる。
「1996」も記念碑的アルバムでしたが、
「THREE」を一度聴くともう「1996」は聴けません。

グランドピアノ (木目) 1102-7
10カ月の娘のためにと購入したのですが、サイズもちょうどいいし、木目も自然でいい感じです。ポロリンリンと鉄琴のような音で、叩けばかなり音量も。細かいタッチにはついてこれませんが、それはそれでいいでしょう。叩くと音が出る、ということが楽しいんでしょうから。
発見が3つ。1)団扇であおぐと、ちょうどビブラホンの様に、音がホワンホワン共鳴します。ミルトジャクソンの気分になれます。原理的に、そうなんでしょ。
2)テレビの前に置いておくと、ちょっとした音取りの時に便利です。キーはそれなりに合ってるので、ああ、こんなコードなんだ、ってことがその場で確認できたりするんですね。
3)10カ月でつかまり立ちの時期ですが、つかまり立ちの高さがちょうどいい。
まだ、子供は、じゃんじゃん手のひらで鍵盤のあたりを叩いているだけですが。
とてもよい買い物をしました。

音楽は自由にする
音楽家・坂本龍一(1952- )が、衝撃を受けた音楽との出会いや関わり方、問題意識など、音楽を巡るこれまでの自分の半生を振り返った一冊。月刊誌『エンジン』のインタビューで語った著者の言葉をもとにした、ひとりの音楽家の個人史です。
インタビューの記事をもとにしたせいでしょうか。文章に格別の味があるといったものではありません。現在の坂本龍一が、過去の自分や出来事を回想した記憶の集積は、ある時期をクローズアップしているといったことはなく、淡々と振り返っていくのですね。文章のアクセントとして写真が多く掲載されているのは嬉しかったのですが、本書の構成や流れが直線的で、面白味に欠けるものだったのが残念。坂本龍一の音楽のテーマや核になっているいくつかのキーワードを掲げ、その視点に立って過去を振り返っていくといった、何かもうひと工夫あって欲しかった気がしました。
本書は時系列順に、次の五つのブロックで構成されています。
◆1952-1969・・・・・・初めてピアノを弾いた幼稚園の頃から、バッハやドビュッシーの西洋音楽の流れを経て、現代音楽や同時代の音楽と出会う高校生まで
◆1970-1977・・・・・・芸大の作曲科に入学した大学生から、細野晴臣、高橋幸宏と三人で結成するYMO前夜まで
◆1978-1985・・・・・・一躍、時代の寵児になったYMO時代から、映画『戦場のメリークリスマス』に参加したYMO散開前後まで
◆1986-2000・・・・・・ベルトルッチ監督の映画『ラストエンペラー』に参加し、アカデミー賞を受賞する体験を経て、ニューヨークに移住し、世界に向けて音楽を発信する二十世紀の終わりまで
◆2001- ・・・・・・ニューヨークで起きた2001・9・11のテロ事件との遭遇から、YMOの再結成、現在進行中の企画、グリーンランドで考えたことなど
なかでも、YMO初期の頃の三人の共同作業、ほかのふたりとの音楽性の違いについて語った文章が興味深かったですね。たとえば、次の件りなどに。
<基本的に、幸宏や細野さんの場合は、音楽性のベースとしてポップスやロックがある。でも、ぼくにはそれがなかった。だから、2人が「あのバンドの、あの曲のあそこの感じ、あのベースとドラムね」とか言って通じ合っているときに、ぼくだけ全然わからないんです。バンドや曲の名前を覚えて、密かにレコードを買って聴いたりしていました。>(p.124)





