
高く手を振る日
辻原登の驚嘆すべき書評に出会い手に取った。
書評の視点は「時間の旨汁」という生の繰り返しの中で実現する生きてきた別個の時間の擦り合わせにより生ずる時間の実感つまり生の充実である。
二人はとうに相方に死別した。再会は5・6年前の大学時代の共通の友人の葬儀であった。
老年の、先の見えた二人の息詰まるような恋物語である。
それは、三回の逢瀬で完結する。最後が、題名の「高く手を振る日」の別れのシーンである。このあたりの分析も鋭い。
緻密で、余計なものがなく深く考え抜かれた構成と抑制の利いた文体とが相俟って一気に読ませる。
まるで、この世というよりあの世から見た出来事のようだ。
とうの昔に小説から遠ざかっていたがレベルの高さに驚き堪能した。
ショスタコーヴィチの弦楽四重奏をボロディンクゥワルテットの演奏で聴く感じだ。
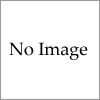
春の道標 (新潮文庫)
新制高校という言葉が耳新しかった頃。安保を巡る政治の季節を眼の隅に入れながら、文芸サークル「夜光虫」で仲間と詩作も試みる高校二年生の倉沢明史。彼には、長く文通を続けている一つ上の幼馴染、見砂慶子がいた。だが、ある時、慶子のほうからそれ以上のものを求める手紙が来る。そこに慶子自身によるエスカレーションを感じた明史の心は徐々に慶子を離れていく。そのうち、通学途上で出会う1人の少女の存在に明史は気が付き始める。その中学生、染野棗(なつめ)に、明史は加速度を増して惹かれていく。
誰かを好きになることで、己と世界が変わることを体験し、そのひとを失うことで、己と世界のすべてもまた失しなわれてしまうことを識る。その、青春のまばゆいばかりの光と翳。だれの人生にも一瞬訪れるだろう輝ける日々、そして絶望。
それを思い出として持つ人も、またその予感を感じる人にも、一度手にして欲しい傑作。






