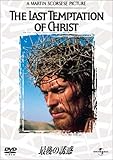
スコセッシ監督のこの作品もまた傑作で、観終わった後に深く感動する。内容はイエスキリストの苦悩と達観を人間的な視点で描くものだが、キリストは神だが同時に人間でもあったので、この物語のような悩みがあってもおかしくは無いだろうし、はりつけにされる意味の解釈も深く納得させられる。神は絶対的な存在だが、凡庸な人間を納得させられなければ象徴とは成り得ないはずで、必要以上に神キリストを美化する傾向はかえって胡散臭く感じさせる。神様は悩める人々の象徴でなければならない。軋轢に屈することなく強い信念を持って貫き、肉体を破壊しても強い精神は破壊できない。自らを犠牲にし罪ある人々を哀れみ、そして許す。常人には理解出来ないレベルの苦行を乗り越えねばそんな境地には達することは出来ないはずで、弱い心を強く刺激する甘い誘惑に悩むことだって当然あるはずだ。公開当時、キリスト教信者から猛抗議があり公開禁止を訴える動きもあったが、細かい表現云々より本質が大切なのではないでしょうか。
あと、音楽について触れておきましょう。ピーターガブリエル(ex ジェネシス 等)は、イギリスのロックアーティストだが、このサントラはCDで何度聴いた事か。中近東を思わせる民族楽器などを駆使した音楽は癒しと神秘に溢れ、木漏れ日のように暖かく包み込む希望に満ち溢れた後光が差したかのようなクライマックスには思わず涙する。どっぷりと浸ることが出来る最高レベルの楽曲群。この映画の価値を更に高める最高のサウンドトラックも忘れてはならない。

オースターのニュヨーク三部作あたりと続けて読むとなんじゃこりゃ?と思うでしょう。SF? と。
解説に書いてあるが、一見SFっぽいんだけれど、モチーフは完璧に現代らしいんです。未来の話じゃない、いまどこかの国で確実に起こりえること、としてオースターは書いてある。
崩壊(しかかっている)国に迷い込んだひとりの女性からの手紙。ですます調の文体と、濃い心理描写と突き詰められた設定。それは現代の寓話にどうしても見えてしまうけれど、だからこそ、「現実」として突き刺さってくる。
生きるのに油断できない生活。意味がない、身を削ってまで、しかもそれが自己保身にしか繋がらない倒錯的な慈善活動。ひとつひとつ現代に還元していくのもおもしろい読み方かもしれないけれど、そのまま読んでみたらどうだろう?
ストーリーテラーとしての才能が怖いくらいに魅せられる傑作。

1989年発表。アラン・パーカー監督の『バーディ』に続くピーター・ガブリエル2枚目のサウンド・トラック・アルバム。
1980年に結成されたWOMADは1982年にWOMADフェスティバルを開催し、着実に成長してきた。ユッスー・ンドゥールのようなスターを産みだし、ワールド・ミュージックの力を知らしめて来たわけだが、ピーター・ガブリエルとWOMADのコラボにより完成した本作こそその極みと言うべきものだろう。
映画『最後の誘惑』に使われた本作は、映画自体がイエス・キリストとマグダラのマリアの愛といったナーバスな題材(まさに今注目されていてる『ダ・ビンチ・コード』の中のシオン修道会の秘密に近い(●^o^●))であったため上映禁止になったフランスのような国もあった。音楽は映画で使うことが出来なかった録音も含まれていて時間をかけまとめ直されたものであり、映画サントラそのものとは若干異なる性質を持っているとも言えるだろう。 何といっても惹きつけられるのは、ピーター・ガブリエルとユッスー・ンドゥールの対比的なヴォイスである。実に深い深い音楽世界だ。

モデルさんのスタイルは良いですね。
ただし特徴のある顔なので、万人受けするかどうかは微妙。
水着の面積は概ね小さめで、作り的にも佳作です。

なぜユダヤの議員ヨセフはイエスの遺体を引き取ったのか、公生涯以前のイエスの人生にはなにがあったのか、イエスの墓はなぜ空だったのか。
日本を代表するイエス研究者、佐藤研さん。けれども、この本には論文だけでなく、著者が「なぜ」「なにが」と想像力を働かせたフィクションが収められているところがユニークです。
論文にも佐藤さん独特の考察が見られます。ひとつは、イエスには「きわめて鋭敏な『罪性』意識があった」(p.45)という点です。「自分がこうした『乞食たち』やそれと類似の者たちの群れの中にいないことをどこか疼きとして感じ、社会的・職業的立場ゆえの〈負い目〉を敏感に感取したに違いない」(p.3)。
しかし、イエスは飛躍したと著者は言います。「自らの罪性に沈む自己の存在が実は『神の王国』によって無限に赦され、生かされるものとして把握された」 (p.47)。
ところで、近代のイエス研究者たちは「イエスを人間として扱いながらも、己のイエス像を徹底的に理想化することで、無意識的にではあれ、かつての『神』としてのイエスの後光を補填してきた」(p.126)と佐藤さんは指摘します。
イエスも人間として成長したはずであり、福音書にもそのプロセスがうかがえるが、それを無視して、そこに語られるイエスのあらゆる姿を無批判に良しとしてきのではないか、と言うのです。
たとえば、「だれでも人々の前で自分をわたしの仲間であると言い表す者は、わたしも天の父の前で、その人をわたしの仲間であると言い表す」(マタイ10:32)などには、威嚇やイエスの自己絶対化がうかがえます。
ところが、ゲツセマネ以降、これが姿を消すのです。「他を威嚇する態度も・・・他者へのあからさまな批判も自己弁明も・・・自己肥大化の言説も脱落している。イエスはただ孤独を貫き、沈黙を守り・・・この『最後のイエス』の姿こそ・・・これまでの自己の姿への訣別ではないか・・・これほどおそろしい『批判』の刃もない」(p.139)。
|